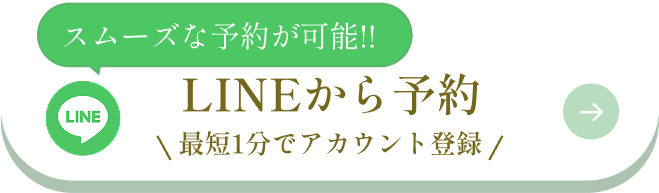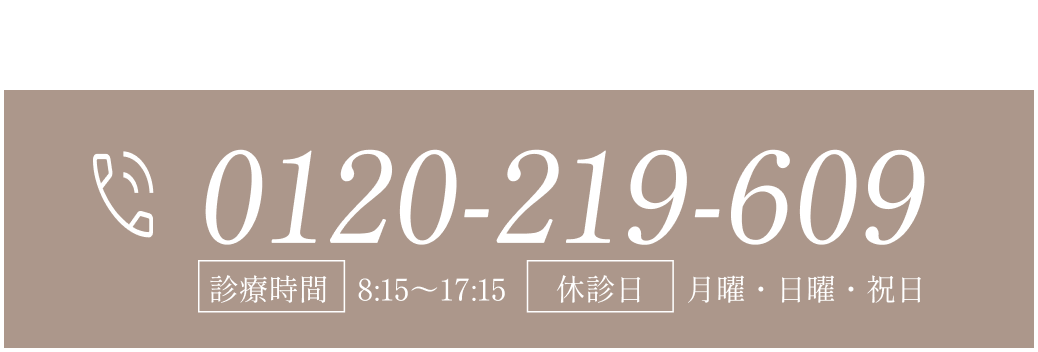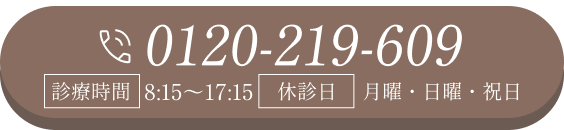バセドウ病の人がやってはいけないことや食べてはいけないものは?

グループ医院
眼形成外科オキュロフェイシャルクリニック 東京
アクセス
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目15−4
ヒューリック銀座一丁目昭和通りビル 8階
電車でお越しの方
浅草線「東銀座駅」A8出口徒歩5分
有楽町線「銀座一丁目駅」10番出口徒歩4分
銀座線「京橋駅」2番出口徒歩4分
診療時間
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
8:15〜17:15
[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。
新前橋かしま眼科形成外科クリニック
アクセス
〒371-0844
群馬県前橋市古市町180−1
フォレストモール新前橋
お車・電車でお越しの方
大型駐車場 完備(フォレストモール新前橋内)
新前橋駅から徒歩7分
診療時間
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
8:15〜17:15
[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。
まぶたとなみだのクリニック千葉
アクセス
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見1丁目1−13
JS Bldg 6階
電車でお越しの方
JR千葉駅から徒歩6分
京成千葉駅から徒歩6分
診療時間
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
8:15〜17:15
[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。
オキュロフェイシャルクリニック大阪
アクセス
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目12-6
EーMA(イーマ)3階
電車でお越しの方
JR大阪駅より徒歩3分
阪急大阪梅田駅より徒歩6分
診療時間
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
8:15〜17:15
[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。
オキュロフェイシャルクリニック京都
アクセス
〒600-8031
京都市下京区貞安前之町589
TM四条寺町ビル4階
電車でお越しの方
阪急電鉄京都線「京都河原町駅」 徒歩3分
市営地下鉄烏丸線「四条駅」 徒歩8分
診療時間
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
8:15〜17:15
[休診日]月曜・日曜・祝日
※水曜は12時まで診療
※当院の診療は完全予約制になります。