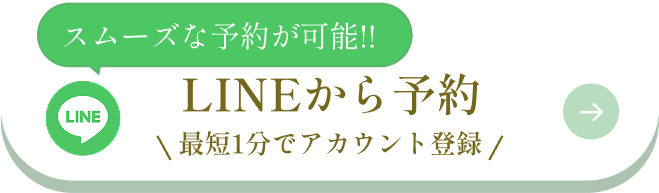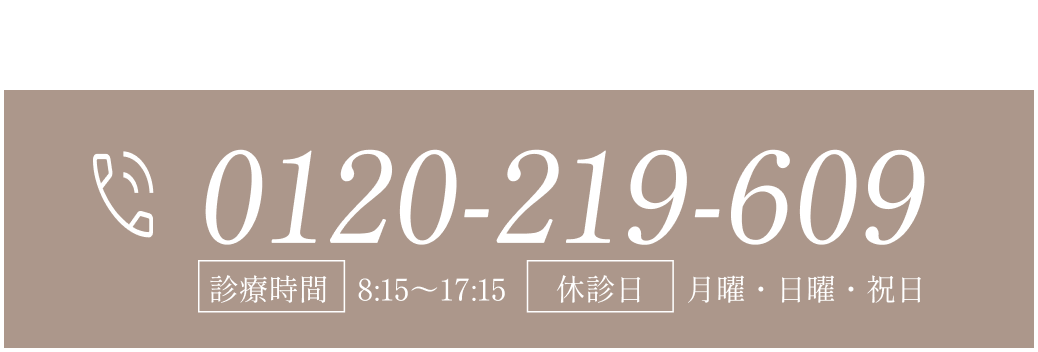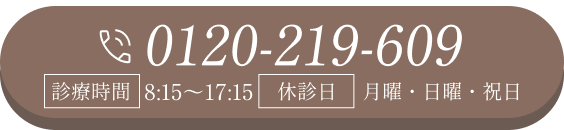バセドウ病が妊娠に与える影響は?赤ちゃんへの影響はある?

グループ医院
眼形成外科オキュロフェイシャルクリニック 東京
アクセス
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目15−4
ヒューリック銀座一丁目昭和通りビル 8階
電車でお越しの方
浅草線「東銀座駅」A8出口徒歩5分
有楽町線「銀座一丁目駅」10番出口徒歩4分
銀座線「京橋駅」2番出口徒歩4分
診療時間
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
8:15〜17:15
[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。
新前橋かしま眼科形成外科クリニック
アクセス
〒371-0844
群馬県前橋市古市町180−1
フォレストモール新前橋
お車・電車でお越しの方
大型駐車場 完備(フォレストモール新前橋内)
新前橋駅から徒歩7分
診療時間
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
8:15〜17:15
[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。
まぶたとなみだのクリニック千葉
アクセス
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見1丁目1−13
JS Bldg 6階
電車でお越しの方
JR千葉駅から徒歩6分
京成千葉駅から徒歩6分
診療時間
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
8:15〜17:15
[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。
オキュロフェイシャルクリニック大阪
アクセス
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目12-6
EーMA(イーマ)3階
電車でお越しの方
JR大阪駅より徒歩3分
阪急大阪梅田駅より徒歩6分
診療時間
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
8:15〜17:15
[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。
オキュロフェイシャルクリニック京都
アクセス
〒600-8031
京都市下京区貞安前之町589
TM四条寺町ビル4階
電車でお越しの方
阪急電鉄京都線「京都河原町駅」 徒歩3分
市営地下鉄烏丸線「四条駅」 徒歩8分
診療時間
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
8:15〜17:15
[休診日]月曜・日曜・祝日
※水曜は12時まで診療
※当院の診療は完全予約制になります。